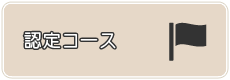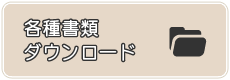グラウンド・ゴルフとは
グラウンド・ゴルフの紹介
1.新しいスポーツの開発
高度な技術を必要とせず、しかも全力を出す場面と、集中力や調整力を発揮する場面がうまく組み合わされており、ルールもごく簡単なことから、初心者でもすぐに取り組めます。
2.理念
- “人間を重視するスポーツ”である
- スポーツに人間を合わせるのではなく、プレーする人にスポーツを合わせるという考えに基づいて考案されたスポーツです。
- “結果を含めた過程を重視するスポーツ”である
- プレーの結果として勝つことに楽しさを感じることは当然ですが、それ以上に、結果に至る過程が大切にされ、プレーヤー同士の交流や触れ合いなどがとても重視されます。
- “自律的な行動を重視するスポーツ”である
- プレーヤーの自律性が重視され、自分自身を審判する公平性や公正さが強く求められます。グラウンド・ゴルフというスポーツは、ルール違反をする人はいないという前提で成り立っています。
3.ゲーム方法
場所によって距離やホールポストの数を自由に設定でき、ルールも簡単なため、どこでも、だれでも手軽に楽しむことができます。
4.グラウンド・ゴルフの特徴
- どこでもできる
-
規格化されたコースを必要としません。
プレーヤーの目的、環境、技能、などに応じて、運動場、河川敷、公園、庭などどこでも、自由にコースを設定することができます。 - 準備は簡単
- ゴルフのように穴を掘る必要がなく、ホールポストを立てるだけで準備は完了です。
- ルールは簡単
- 他のスポーツに比べて、ルールがきわめて簡単で、一度プレーすれば覚えられます。
- 時間の制限がない
- ゲームの時間が決まっていないので、時間に制約されることなく、技能の水準や仲間の数、あるいはコースの特性に応じて、プレーを楽しむことができます。
- プレーヤーの数に制限がない
-
グラウンド・ゴルフは1人でも、あるいは場所さえあれば一度に何百人もの人がプレーを楽しめます。
ボールが空中を飛ぶことはないので、ホールの設置場所を工夫すれば、各ホールから同時にスタートしても、安全にプレーすることができます。 - 審判はあなた自身
- ゲーム中の審判はプレーヤー自身が行います。判定が困難な場合には、同伴プレーヤーに同意を求めます。
- 高度な技術がなくてもできる
- グラウンド・ゴルフの技能は他のスポーツと同じように、トレーニングによって向上します。しかし、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要としません。子供から高齢者まですべての人が、楽しくプレーすることができます。したがって、グラウンド・ゴルフはファミリースポーツとして楽しむ条件をすべて備えたスポーツです。
グラウンド・ゴルフのルール
第1章 エチケット
第1条 プレーヤーは、自分のプレーが終わったら、すみやかに次のプレーヤーの妨げにならない場所に行く。
- コースを早くあける
- プレーヤーは、自分のプレーが終わったら、次のプレーヤーの妨げにならない場所にすみやかに移動しましょう。
- 自分のボール付近に移動
- 自分の打ったボールの周辺に移動しますが、他の人のプレーの妨げにならないように注意しましょう。
第2条 プレーヤーは、同伴のプレーヤーが打つときには、話したり、ボールやホールポストの近くやうしろに立たない。また、自分たちの前を行く組が終了するまで、ボールを打たない。
- 他のプレーヤーが構えたら静かに
- 話しながらプレーするのはグラウンド・ゴルフの楽しみの一つです。しかし、プレーヤーが打つために構えたら、大声で話したり、笑ったり、動き回ることはやめましょう。
- 安全に配慮を
- 打とうとしているプレーヤーの近くにいると、スイングしたクラブに当たってしまう危険性があります。お互い十分に注意してプレーしましょう。
- 前の組が終わってからプレー
- 自分たちの前を行く組が終了してからスタートマットの上にボールを置きましょう。
第3条 プレーヤーは、自分の作った穴や足跡を直して行く。
- 自分で直して移動
-
天候や施設の状況によっては、プレーヤーの移動によって穴や足跡ができることがあります。
プレーヤーは可能な範囲で自分で作った穴や自分の足跡を直してから移動することがエチケットです。
ぬかるんでいる時は、ボールが通ると思われるライン上は、できるだけ避けて移動するようにしましょう。
第2章 ゲームに関するルール
第4条 ゲーム ゲームは、所定のボールを決められた打順にしたがってスタートマットから打ち始め、ホールポスト内に静止した状態「トマリ」までの打数を数えるものである。
- 打順を決めてゲームを始めます
-
- ゲームを始める前に、どういう打順にするかきめます。
- 打順については、第1打目から「トマリ」まで1打ずつ同じ打順でプレーします。
- 連打
- 一人の人が「トマリ」になるまで続けて打つ、いわゆる連打は認められません。
- 「トマリ」とは
-
トマリとはボールがホールポストの底円の内側に半分以上が入って静止した状態をいいます。また、ホールポストの上円に乗った場合も「トマリ」となります。
ホールポストの底円の真上から見て判定します。 - 打順のきめ方
- 大会や講習会では主催者が決定し参加者に通知します。それ以外の場合はプレーヤーで話し合ってきめます。
第5条 用具 クラブ、ボール、ホールポスト、スタートマットは定められたものを使用しなければならない。
- 用具は定められています
- クラブ、ボール、ホールポスト、スタートマットは、日本協会用具標準規則で定められた認定用具を使用しなければなりません。
- 用具の改造は
-
- クラブはグリップテープなどを巻いたり、規定の範囲内で短くすることはできますが、それ以外の改造は禁止です。これは安全性を考慮したものであることを理解することが大切です。
- クラブやボールに目印やイニシャルを付ける場合は、クラブやボールの機能を変えない、自分のものが見分けられる程度のものにしてください。
- 公式大会は認定品で
- 公式大会、講習会では用具は全て日本協会認定品を使用しなければなりません。
第6条 ゲーム中の打球練習 プレーヤーは、ゲーム中いかなる打球練習も行ってはならない。本条の反則は1打付加する。
- ゲーム中の打球練習
-
ボールを打つ練習をしたら、反則で1打付加です。スイングは良いのですが、ボールを実際に打つのは反則です。
スイングの練習をする時は周囲の安全に十分注意し、また、他のプレーヤーがプレーを開始したらすぐにやめ、静かにしなくてはなりません。 - 大会や講習会時の打球練習
-
大会や講習会ではゲーム開始前のコース内での打球練習については、主催者の指示にしたがってください。
指示がなければコースでの打球練習はしないのがエチケットでしょう。
第7条 援助 プレーヤーは、打つとき足場を板などで作ったり、人に支えてもらったりするなど、物的・人的な援助やアドバイス、あるいは風雨からの防護を求めたり、受けたりしてプレーしてはならない。本条の反則は1打付加する。
- 援助を受けてはならない
-
- グラウンド・ゴルフは自主性を重視するスポーツです。雨が降るので傘をさしてもらった、スイングの妨げになる木の枝を押さえてもらった、足元が不安定なのでうしろから支えてもらったなどの反則は1打付加となります。
- 障害のある人から求められたら、マークなどしてあげることは差し支えないでしょう。
これらのことは、プレーが始まる前に同伴プレーヤーで確認しておきましょう。
第8条 ボールはあるがままの状態でプレー プレーヤーは、打ったボールが長い草や木のしげみなどの中に入ったとき、ボールの所在と自己のボールであることを確かめる限度においてのみ、これらのものにふれることができる。草を刈ったり、木の枝を折ったりしてプレーしてはならない。本条の反則は1打付加する。
- ボールはあるがままの状態で
-
ボールが長い草やしげみの中に入って打てそうもない状態のときがあります。そんなときボールのそばの草を踏みかためたり、手で抜いたり、木の枝を折ったりして、条件を良くしようとする人がいますがこれは認められません。あくまでもあるがままの状態でプレーすることです。
これらの反則は1打付加となります。 - 障害物は取り除けません
-
- どんなにスイングがしにくい状況に置かれても、ボールの周辺に手を加えて自分に有利にしてはならないということですから、ボールとホールポストの線上に石、小枝、砂などの障害物があっても、取り除いたりしてはいけません。
- プレーが始まれば、地面に落ちている木の枝、小石、虫類、動物の糞なども障害物とみなされるので取り除くことはできません。
これらのものはプレーが始まる前に取り除きましょう。
- 障害物
- 他のホールポストやコース内に設置されているものはすべて動かせない障害物とみなします。
第9条 ボールの打ち方 プレーヤーは、ボールを打つとき、クラブのヘッドで正しく打ち、押し出したり、かき寄せたりしない。本条の反則は1打付加する。ただし、から振りの場合は打数に数えない。
- ボールの打ち方
- ボールをヒットしないで引きずるように打ったり、二度打ちしたり、まわして打ったり、押し出し、かき寄せで打ったりしてはいけません。これらの反則は1打付加となります。
- から振り
-
- から振りとは、スイングしたグラブが直接ボールに触れていないことをいいます。
から振りの場合は打数に数えません。
- から振りとは、スイングしたグラブが直接ボールに触れていないことをいいます。
第10条 紛失ボールとアウトボール プレーヤーは、打ったボールが紛失したり、コース外に出たときは1打付加し、ホールポストに近寄らないで、プレー可能な箇所にボールを置き、次の打を行わなければならない。
- 紛失ボール
-
草むらや林の中に入り探しても見つからない場合は、ボールが見えなくなった場所からホールポストに近づかない箇所にボールを置いてプレーします。
この場合は、1打付加となります。 - アウトボール
-
ボールがコース外に出たり、池や川、排水路などの溝に入ったり、障害物があったりしてどうしても打てない場所に入った場合は、ボールの落ちた所や打てない場所からホールポストに近づかない場所にボールを置いてプレーします。
この場合は、1打付加となります。
第11条 プレーの妨げになるボール プレーヤーは、プレーの妨げになるボールを、一時的に取り除くことを要求することができる。取り除くのは、ボールの持ち主であり、その際ホールポストに対して、ボールの後方にマークをして取り除かなければならない。
- ボールを取り除きます
-
自分がプレーしようとしたとき、そのままプレーすると他のプレーヤーのボールに当たってしまいそうな場合はボールを取り除くことを要求することができます。
自分のボールが他のプレーヤーのプレーやボールに影響を与えると思われる場合は、他のプレーヤーから要求される前にマークして取り除くのがエチケットです。ライン上やその延長線上はマークするようにしましょう。 - 取り除き方
-
- マーカーを置いてからボールを取り、ボールを置いてからマーカーを取りましょう。
- マーカーは、プレーの妨げにならないものを使いましょう。あまり大きくても、厚みがあってもいけません。お金をマーカーとすることはやめましょう。
第12条 他のプレーヤーのボールに当たったとき プレーヤーは、打ったボールが他のプレーヤーのボールに当たったときは、そのままボールの止まった位置からプレーを続ける。当てられたプレーヤーは元の位置にボールをもどさなければならない。
- ボールがボールに当たったとき
- ゲーム中は予測できないことが発生します。注意していてもボールを打ったとき他のプレーヤーのボールに当たることがあります。その場合は、当てられたプレーヤーはボールを正しく元の位置にもどし、その位置からプレーします。当たったボールはそのまま停止したところから次のプレーを行います。
- 周囲のボール、観客に注意
- ゲーム中は、他のプレーヤーのボールや観客に十分注意するとともに、プレーに影響を与えると思われるボールはマークして取り除きましょう。
第13条 止まったボールが風によって動いたとき プレーヤーは、打ったボールが動いている間は、ボールを打ってはならない。風によってボールが動いたときは、静止した場所からプレーをし、動いてホールポストに入った場合はトマリとする。
- 自然に動いたとき
-
グラウンド・ゴルフのボールは強風でも動いたりしないよう工夫されていますが、自然は人間の力では計り知れないところがあり、絶対にボールは風で動いたりしないという保障はありません。風の強い日にもプレーしなければならない時もあります。
風によって動いたらやむを得ないこととし、止まった位置からそのまま打つということです。
ひどく無情なようですが、風に吹かれてホールポストに入ったら、これは「トマリ」ですので不運ばかりではないわけです。 - 不可抗力でなく動いたとき
-
- 自然が原因でない、次の場合は動いたボールを持ち主が元の位置にもどしてプレーを進行させます。
- 犬や鳥などの動物がボールにいたずらをして動かしたとき
- 観客などが何かのはずみでボールにふれ動いたとき
- 他のプレーヤーが自分のボールと勘違いして打ったとき
第14条 第1打がホールポストに入ったとき プレーヤーは、打ったボールが1打目でトマリになったとき(ホールインワン)は、合計打数から1回につき3打差し引いて計算する。
- 3打引きます
- 第1打が「トマリ」となったときは、ホールインワンといいます。合計打数から1回につき3打引きます。
- ホールインワンのスコア記入
- ホールインワンになったときのスコアカードの記入は、1打打ったことには間違いないので①または㊀と記入し、合計欄にはホールインワン1回につき3打を引いた打数を記入する。
- スコアカード
-
日本協会では標準スコアカードを提示しています。
なお、具体的な記載方法は講習会や大会では主催者が決定し、参加者に通知します。
それ以外の場合はプレーヤーで話し合って決めます。
第15条 ゲーム中の判定 ゲーム中の判定はプレーヤー自身が行う。ただし、判定が困難な場合は同伴プレーヤーの同意を求める。
- グラウンド・ゴルフの判定は自分自身で
-
グラウンド・ゴルフは第三者の審判員がいなくてもプレーできるよう、また、プレーヤーがお互いに審判、判定しながらプレーを楽しむことができるようなスポーツとして考案されました。
その趣旨を生かすため平成9年4月から新たに15条を明記しました。 - 審判は自分自身
-
- 第三者の審判員のいないスポーツです。つまりプレーヤー個々が審判の役割を果たし、自分の良識に基づいて他のプレーヤーと協力し合う自主性を重んじるスポーツなのです。この精神を決して忘れず、プレーを楽しんでください。
- 自分で判定に迷ったら、同伴プレーヤーの同意を求めて判定しましょう。
- 判定は公平に
-
判定に当たっては、常に次のことを心がけましょう。
- ルールをしっかり理解する。
- 自分に有利になるような判定はしない。
- 自分で判定できないときは同伴プレーヤーの意見を求める。
第16条 標準コース 標準コースは、50m、30m、25m、15m各2ホールの合計8ホールで構成する。
- 公式大会及び認定コース
-
- 同じ距離を連続させない標準コースをコース設定します。(8ホールから1ホールについても同様)
- 上記以外のコース
-
- グラウンド・ゴルフの一つの魅力はコースを自由に設定でき、また、場所を選ばないということでしょう。
- たとえば運動場、河川敷、公園、庭……、障害物や起伏があっても楽しめます。その場所に合わせてスタートからの距離、ホール数を決めればよいのです。場所、条件、参加者に応じてホール数、距離など適切なコースを設定することが望ましいのです。
- コース設定の仕方
-
- ホールポストは、3本の脚のうち2本がスタートマットの方向に開いた形でセットします。
- 砂や草などで底円が埋まらないよう注意して平らにセットします。
- ホールポストはプレー中に動いたり、倒れたりしないようにできるだけU字ピンや、おもりなどで固定しましょう。
- 距離は、スタートマットのティーからホールポストの鈴の中心までを測ります。
- ゲームの快適さや安全性を高めるためにコースセットの際は、ホールポストとスタートマット及びホールポストとホールポストの距離を5m以上(50mのホールでは、それ以上)とることを心がけましょう。